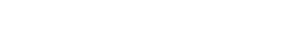社長メッセージMESSAGE

“測る”“動かす”
ものづくりを武器に
新たな価値をともに創り出そう
代表取締役社長

01多摩川精機の誕生
多摩川精機は1938(昭和13)年、東京の蒲田区(現東京都大田区)に流れる多摩川のほとりで創立しました。
創業者である萩本博市は飯田市の隣にある泰阜村の生まれで、幼少の頃から教師を志していました。東京府青山師範学校(現東京学芸大学)を卒業後、小学校で教職に就きましたが、先輩の先生から「君は教員よりも技術者に向いている」と言われたことをきっかけに自らも「もっと技術を追求したい」という思いに目覚め、東京高等工業学校(現東京科学大学)で改めて学びを深めます。卒業後、航空計器や工作機械の大手メーカーだった北辰電機製作所へ就職して技術を磨き、一部の部品製造を引き受ける形で独立しました。
当時、創業者の出身地であるここ飯田・下伊那地域は主に農業や養蚕を収入の柱とした貧困の地でした。「工業で収入が得られれば皆の生活が楽になるはず」「郷土の発展のためには工業振興しかない」と考えた創業者は、1942(昭和17)年、飯田市内に飯田工場を新設。最盛期には約2,000人の社員を擁し、大きな発展を遂げました。
しかし 、戦争の終結により転機が訪れます。敗戦による航空機産業からの撤退により仕事は減り、社員は24人にまで激減。それでも創業者は、車座になり途方に暮れる社員の前で「多摩川精機は『技術を売る』会社であり、最先端の技術を追求していけば陳腐化しない」と社員を鼓舞し続けました。この時、貫き通した「技術を育て、技術を売る」姿勢は当社の礎となり、現在も脈々と受け継がれています。
02技術で新たな市場を切り開く販路
戦後、一時は危機的な状況に陥った当社でしたが、軍事・航空で培った高精度技術を船舶に応用し、高度成長期以降は工業の自動化にも貢献。フロッピーディスクやプリンタなどOA機器に使われるモータの製造も手掛け、後にこれらの技術をアミューズの世界に応用させて新たな販路を開くなど、時代の変遷に合わせピンチをチャンスに変えて歩んできました。その対応力や技術力が認められ、1997(平成9)年に登場した世界初の量産ハイブリッド車「プリウス」に、基幹部品として当社の角度センサ「シングルシン」が搭載され、以降続く自動車のハイブリッド、EV化の流れの中でも、多様なニーズに応え続けています。
現在も当社は、制御装置の角度精度の向上に挑み続け、Defense Application(防衛、航空、宇宙)、Car Application(車載、鉄道)、Factory Application(工場の自動化用機器)のそれぞれの分野で成長を続けています。技術を応用し、事業領域を広げることで経済の停滞や不安定な国際情勢の中でも安定した経営を可能にしています。
また、「郷里に産業を根付かせたい」という創業者の思いは飯田工場にとどまらず、縁があって進出した青森県八戸地区の5つの工場をはじめ、中国の蘇州、ベトナムのハノイ近郊に新設した工場など、各地域も大切な拠点と捉えています。社員、グループ会社、協力会社、そして各地域とも力を合わせながら世界で戦うことのできる強い企業を目指しています。

03新たな経営理念。
そして「未来の種をまき、対話で育てる」
当社ではこのたび新たな「経営理念」を定めました。「経営理念は経営者のためのものだ」という発想もあるかもしれませんがそれは違います。社員全員が理念を深く理解し、納得し、共感することでそれぞれの立場から経営に関われることを目指し、具体的なアクションにつながる経営理念を定めたのです。
私たちのミッションは「“測る”“動かす”で明日の世界をつくります」。これが当社の存在意義でもあります。そのために目指す将来像として、技術の探究とニーズをつなぎ、社会に役立つ商品を提供する「活きるものづくり」、お客様や協力会社と良好な関係を構築し「頼られる存在」になること、また会社の発展を通じて地域社会に貢献し「地域と共に」歩むことを掲げています。
また、イノベーションには組織の多様化も必要です。違いを強みとし、アイディアを共有する中で、個人ではなし得ない大きな成果が生まれます。お互いを尊重し、高め合うために感謝の気持ちを言葉にすること、何か起こった際には必ず現地に足を運び、自分の五感をフルに働かせながら解決や改善を図る姿勢などを「大切にしたい価値観」として共有していきます。
この経営理念につながるよう、2025年から3年間のビジョンとして描いたのが「未来の種をまき、対話で育てる」です。当社で扱う防衛、宇宙、民間航空、車載、鉄道などの各商品は、簡単に実現できるものではありません。種をまき、実ができるまでに10年以上かかることもあります。種をまくには畑(市場)を探す必要があり、種が芽を出し、根を張るためには働く社員の思いやチームワークも必要です。
トップダウンでは限られた発想しか生まれません。私自身も率先して全社を巡り、社員の言葉に耳を傾ける活動を続けています。同じ目線で話を聞き、対話を活性化させ、意思の疎通をはかりながら皆の力でビルドアップしていきたいと考えています。
04「多摩川精機で働けてよかった」そう社員が思える会社に
会社が成長し、前進していくためには社員一人ひとりの力が欠かせません。全員が、自らの業務に力を尽くし、思いを共有し、努力を重ねることで世界を動かすことができるのです。
私が常に考えているのは、社員が仕事を勤め上げ、退職する際に「多摩川精機で働けてよかった」と満足し、後輩へバトンタッチできるような会社でありたいということ。そうなるための良い場所や働きやすい環境を提供することが経営陣の役目であると考えています。
また、教育者でもあった創業者の思いを受け継ぎ、人材育成に対して前向きに取り組んでいるのも当社の特徴です。資格取得のサポートや学びの場の提供をはじめ、社会人大学院進学支援制度を利用して大学院に通い、修士号や博士号を得ている社員も多数います。積極的に学ぶ姿は周囲の向上心にもつながりますし、自らの成長の糧にもなるはずです。加えて、ヨーロッパや中国、ベトナムなど海外に拠点があり、希望があればグローバルな仕事に挑戦できる環境も整えています。

05来たれ!多摩川精機へ
私は学生の時、男声合唱団に所属していました。コーラスではベースの音が正しくなければ、セカンドもトップも和音に乗ることができません。これはクラシックの世界でも同じこと。指揮者のタクトに合わせて声や音が重なる、そうしたハーモニーの中でクリエイティブなものが生まれる世界を、この会社でも実現していきたいと考えています。
また、ぜひ皆さんにも感じて欲しいのが「ものづくりから得られるよろこび」です。私は大学を卒業後、東京の企業で働いたのち、故郷へUターンして多摩川精機へ入社しました。病床の母親のことを考えたのが大きな理由でしたが、自分が働いてみたいと感じられる会社があったこともUターンを決意できた理由の一つでした。
入社して最初に手掛けたのが「エンコーダ」の設計です。一番面白いと感じたのは、描いた図面がきちんと「もの」になり、お客様が購入して「利益」が生まれることでした。世にないもの、難しいものほど利益は高くなり、良いものを作ればお客様に喜ばれて次の依頼へつながります。そうしたビジネス感覚は学生時代や前職の研究所時代には味わうことのできないものであり、ワクワクしたことを今も覚えています。
技術革新が次々と起こるこの時代においては、常に新たなチャレンジが求められます。当社は、長野県の山地に本社を構えながら、世界的な大手企業のTier 1 サプライヤー(一次サプライヤー)として最先端の技術を提供している大変珍しい会社です。それが叶うのも、技術を資産として挑む姿勢があるからこそ。お客様のニーズに応える商品を生み出す一方で、次の時代を見据えて新たな研究をし続ける、その両輪をバランスよく回していくことも意識しています。
リニア中央新幹線の開通を控え、本社のある飯田下伊那地域も今後、大きく変化します。開通後は東京、名古屋、大阪など都市圏のいずれにもアクセスの良い中間地域として、より住みやすい環境も生まれるはずです。
地方から世界、そして宇宙へ。技術を武器に未来を切り拓き、新たな価値をともに創り出していきましょう。新しいことに物怖じせずトライできる力が会社を進化させる原動力になります。来たれ!多摩川精機へ。皆さんのチャレンジをお待ちしています。
エントリーENTRY
まず話を聞きたい方
エントリーされた方に、説明会やインターンシップなどの採用に関する情報をご案内します。
説明会・インターンシップの申込
説明会やインターンシップなどのイベントを開催しています。
応募フォーム
ご応募される方はこちらから。皆様のご応募をお待ちしています。
新卒採用に関するお問い合わせは、
こちらから。